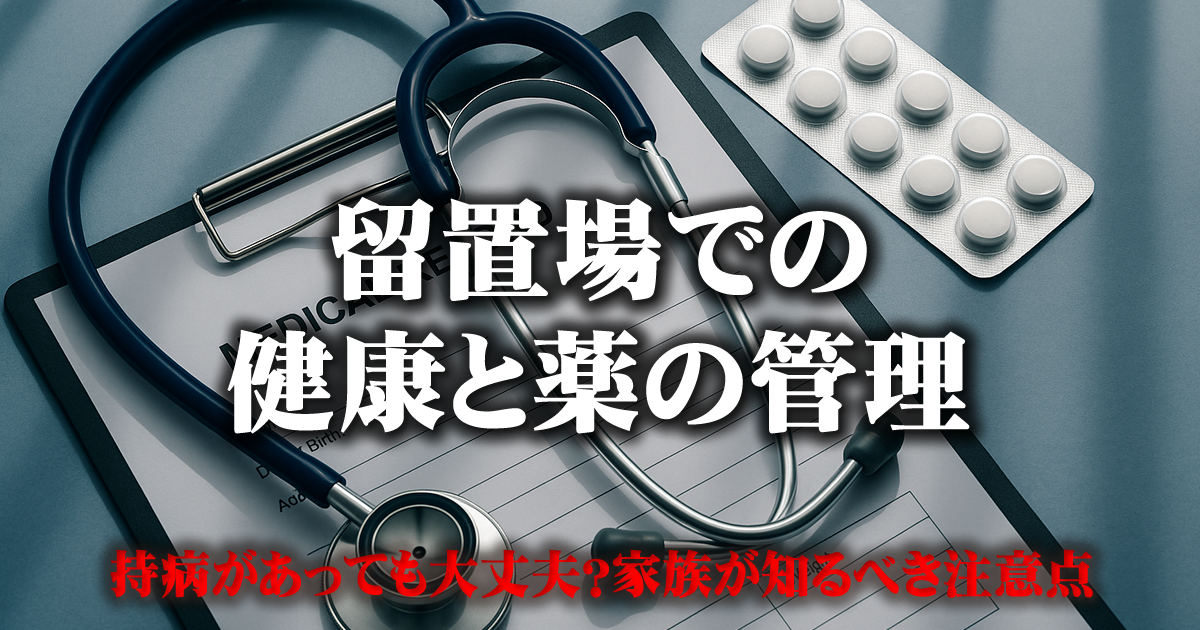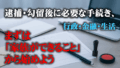家族の逮捕と健康面の不安
家族が逮捕され、留置場に勾留されることは誰にでも起こり得ます。そんなときに心配になるのが「健康は大丈夫だろうか」という点です。特に持病や服薬が必要な家族であれば、なおさら不安が強くなります。本記事では、留置場での健康管理の仕組みや薬の扱い、家族としてできるサポートについて解説します。
留置場での健康管理の基本的な仕組み
留置場は警察署の中にあり、逮捕直後の人が収容される場所です。原則として、収容される人の安全を守るために健康管理体制が整えられています。警察官が日常的に様子を確認するほか、体調不良があれば医師の診察につなげられる仕組みもあります。
ただし、病院のように24時間体制で医師や看護師が常駐しているわけではありません。必要に応じて外部の医療機関へ搬送される形になるため、健康上の不安がある場合は、家族や弁護士を通じてしっかり情報を伝えることが大切です。
勾留されている本人には、留置場に入る際に健康管理体制のことの説明がされますが、本人にとってはそれどころではなく、うわの空で聞き逃してしまっていることが多いようです。
家族から、面会時や手紙のやりとりで、留置場での健康管理の体制のことや、健康診断があること、体調不良はすぐに留置場管理官に相談することができるということを伝えてください。
持病のある人が逮捕された場合の流れ
逮捕時に持病を抱えている場合、本人が警察に申し出ることで、記録に残されます。警察署の担当者や医師が確認を行い、服薬や治療が必要かどうかを判断します。
例えば糖尿病や高血圧など、継続的な治療が欠かせない病気は「医師の指示に基づく対応」が基本です。ただし、本人が正しく伝えられない場合や、警察が状況を十分に理解できない場合もあるため、家族からの補足が非常に重要になります。
逮捕によってパニックになり、持病のことや常用薬があることを伝え忘れてしまっていることがありますので、家族や担当の弁護士から、留置場担当官に伝えることは大切です。
薬の持ち込みはできる?警察・医師の対応
家族が心配して「薬を持っていってあげたい」と考えるのは自然なことです。しかし、留置場には自由に薬を差し入れることはできません。薬の扱いは非常に慎重で、必ず医師の診断や処方が必要になります。
具体的には、家族が「この薬を常用している」と警察に伝えると、必要に応じて病院を受診し、正式に処方してもらった薬が本人に渡される仕組みです。勝手に薬を差し入れることはできませんが、家族がかかりつけ医や薬の情報を提供することで、円滑に対応してもらいやすくなります。
逮捕時に所持していた常用薬も、そのまま留置場内で服用できない場合があります。
警察指定の医師や医療機関の診断をもって処方された薬でないといけない場合がほとんどです。
糖尿病や高血圧など生活習慣病のケース
生活習慣病を抱えている人は、服薬や食事制限が欠かせません。留置場では食事の内容を本人の病状に合わせて調整することは難しいのが現実ですが、薬の服用については医師の判断により継続されます。
例えば糖尿病でインスリン注射が必要な場合、医師の管理下で注射が行われます。血圧管理のための降圧剤も、必要と判断されれば服薬が認められます。家族は「普段どの薬をどのように使っているか」をできる限り正確に伝えることが重要です。
高血圧、糖尿病、脂質異常症、腎臓病などの生活習慣病を抱えている場合は、服薬が認められるだけではなく、食事も塩分が制限されたものに変更されたりと、考慮されます。
精神疾患や心の病気を抱える人の対応
うつ病や統合失調症、不安障害などの精神疾患を抱えている場合、逮捕・収容という環境変化は大きなストレスとなります。症状が悪化しやすく、自傷行為などのリスクもあるため、警察や医師の細心の注意が払われます。
精神科の薬についても、本人が以前から服薬していた事実や診断書、処方情報を家族が伝えることで、必要な治療が継続されやすくなります。精神的に不安定なときは、医師の判断で専門の医療機関に移される場合もあります。
逮捕によって、不安が大きくなることで、自殺を含めた自傷行為などを防ぐために、薬の服用はもちろん、不安定になりやすいことを留置担当官に伝え、見回りの強化や、病院への通院や入院が必要と判断される場合は、弁護士などを通じて対応していただけるようにお願いすることも考慮してください。
留置場での定期健康診断と体調不良時の対応
留置場では、月に1~2回程度、医師による健康診断が行われます。診断といっても病院での精密検査のようなものではなく、簡易的なチェックが中心です。
この場では、心身の異常や持病に関する相談、薬の処方をお願いすることができます。例えば、慣れない環境で強いストレスや不眠が続き、重度の睡眠障害がある場合には、睡眠導入剤などを処方してもらえることもあります。
また、体調が著しくすぐれないときは、定期健診を待たずに必ず留置担当官へ申し出ましょう。必要に応じて外部の専門病院で診察や治療を受けられる場合があります。
重要なのは「自ら申し出ること」です。警察や医師にきちんと伝えることで、健康を守るための対応が行われるのです。
簡易的な定期健診では、流れ作業的に診断されることもあるため、体調不良の場合は、自発的に医師に症状を伝える必要があることを、家族から教えてあげてください。
留置場での薬の管理と服薬の流れ
留置場では、薬の管理は本人ではなく留置場担当官によって厳格に行われます。薬を自由に所持したり、自分の判断で服用することはできません。
個人別に医師から処方された薬は、医師の指示に従って「毎食後」や「就寝前」などの決められたタイミングで担当官から渡されます。渡された薬はその場で服用し、しっかり飲み終えたかどうかを確認するために、口を開けて見せるよう求められることもあります。
また、留置場には市販の風邪薬や頭痛薬、うがい薬、軟膏なども常備されており、体調に応じて担当官へ申請することで使用することが可能です。薬の利用については、必ず担当官を通す仕組みになっているため、安心して申告することが大切です。
口を開けてしっかり飲み終えたかを確認するのは、薬の服用管理はもちろんのこと、他者への受け渡し等を防ぐためでもあります。
家族が警察に伝えておくべきこと
健康上の不安があるとき、家族が警察に伝えるべき情報は次のとおりです。
- 持病の有無(糖尿病、高血圧、心臓病など)
- 普段服用している薬の名前と量
- かかりつけ医や病院の情報
- 精神疾患や過去の治療歴
これらをできる限り正確に伝えることで、適切な医療につながる可能性が高まります。
健康面で不安が強いときの相談先
家族だけで抱え込む必要はありません。健康面で不安が強い場合は、以下のような相談先があります。
- 弁護士(接見を通じて警察に伝えてもらえる)
- 留置場の担当警察官
- 人権相談窓口や法務省の人権擁護局
- 精神保健福祉センター
- 公的な機関や専門家を通じることで、安心できる情報や対応を得られやすくなります。
差し入れできるもの・できないもの
家族として「食べ物や薬を持っていきたい」と思うのは当然ですが、差し入れには厳しい制限があります。基本的に薬やアルコール、刃物など危険物は持ち込めません。食品も認められません。
一方で、書籍や衣類などは差し入れ可能なことが多いです。健康管理に直結する薬については、必ず警察や医師を通じての手続きが必要となります。
また、コルセットやサポーターなどの医療器具に関しては、本人の身体に合致したものであれば差し入れができる場合があります。
留置場として、差し入れできるものとできないものがあると同時に、コルセットやサポーターなどの医療器具、眼鏡などは差し入れができる可能性が高いです。
家族が安心のために知っておきたいこと
逮捕は家族にとって大きな衝撃です。その中でも健康や持病に関する不安は特に切実です。
留置場では基本的な健康管理が行われており、必要があれば医師の診察や外部病院への搬送も可能です。ただし、家族が正しい情報を伝えないと十分な対応が受けられないこともあります。
持病や薬の情報、かかりつけ医の連絡先などを早めに伝え、必要に応じて弁護士や専門機関に相談することが安心につながります。
さしいれやでも、コルセットやサポーター、眼鏡といった物品の差し入れをサポートさせていただきますので、お気軽にご相談ください。