家族が逮捕・勾留されてしまうと、離れて暮らしていた自宅には本人宛ての郵便物が次々と届き溜まってしまいます。
放置すれば、税金・銀行・役所関係などの重要書類が期限切れになるおそれも。
この記事では、一人暮らしの家族が逮捕された場合に、家族が郵便物を受け取り・転送する方法をやさしく解説します。
逮捕・勾留中に届く郵便物の扱い
逮捕・勾留中であっても、本人の住所宛てに郵便物は通常どおり配達されます。
ただし、本人が不在のため受け取れず、郵便受けにたまってしまうことが多いです。
また、書留や簡易書留など対面での受け取りが必要な郵便物は、本人不在のため受け取りができず、一定期間を過ぎると差出人に返送されます。
この状態が続くと、銀行口座の停止、公共料金の未納、行政手続きの期限切れなど、後々のトラブルにつながるおそれがあります。
そのため、家族が早めに郵便物の管理を始めることが大切です。
家族が郵便受けから郵便物を取り出すのは問題ない?
本人が一人暮らしをしていた場合、郵便受けに投函された普通郵便やチラシ類を家族が取り出すこと自体は、特に違法ではありません。
ただし、封を開けて内容を確認することは「信書の開封」にあたる可能性があるため注意が必要です。
届いた郵便物は開封せずに封筒のまま保管し、差出人をメモしておくとよいでしょう。
中身を確認する必要がある場合は、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。
本人にすでに弁護士がついている場合は、弁護士に差出人のメモを渡す又は伝えることで、本人にどのような郵便物が届いているのか、判断することができます。
郵便局での「転送届」手続きの流れ
本人が勾留中で長期不在になる場合、郵便局の「転送届」を利用することで、郵便物を家族の住所へ送ってもらえます。
手続きの基本
- 郵便局窓口、またはインターネットの「e転居」で申請できます。
- 転送期間は原則1年間(更新も可能)。
- 本人確認書類(免許証など)が必要です。
家族が代理で手続きする場合
本人が勾留中で長期不在になる場合、家族が代理で「転送届」を提出することができます。
【手続きに必要なもの】
- 本人の署名入り委任状
- 本人の本人確認書類(コピー)
- 代理人(家族)の本人確認書類(原本)
ただし、逮捕・勾留中の本人が委任状を用意できないことも多いでしょう。
そのような場合は、郵便局に事情を説明すれば、柔軟に対応してもらえることがあります。
また、担当弁護士に相談することで、弁護士経由で委任状が作成できることもありますので、確認してみてください。
「逮捕・勾留中」と伝えたくない場合
知り合いがいるなどの理由で、「逮捕・勾留中である」と詳しく説明したくない場合もあると思います。
その場合は、無理に正確な理由を伝える必要はありません。
郵便局では、
- 「本人が長期不在」
- 「施設等に滞在中」
- 「しばらく帰宅できない事情がある」
といった説明でも手続きは可能です。
転送届の目的は、あくまで「不在中に郵便物を受け取れないため、転送を希望する」という事実の確認にあります。
個人の事情を詮索されることはなく、局員もプライバシーに配慮して対応してくれます。
✅ 伝え方の例
「本人がしばらく帰宅できないため、家族が代わりに郵便物を受け取りたい」
「本人が長期不在中で、郵便物がたまってしまうので転送をお願いしたい」
このように伝えれば、事実を偽らずに手続きを進めることができ、家族のプライバシーも守れます。
まずは最寄りの郵便局に相談し、必要書類や手順を確認してみましょう。
遠方に住む家族の郵便転送はできる?
たとえば、逮捕された本人が東京で一人暮らし、家族が京都に住んでいるといったケースでは、
「京都の郵便局で転送届を出しても意味があるのか?」という疑問が生まれます。
結論として、転送届は本人が住んでいた住所を管轄する郵便局で処理されます。
そのため、遠方に住む家族が手続きを行う場合は、次の方法が現実的です。
- 現地の郵便局に電話で事情を説明し、必要書類を確認する。
- 書面での委任状・本人確認書類を郵送でやりとりする。
- 郵便局の指示に従って、代理で転送手続きを進める。
郵便局では「代理申請」を想定しており、電話で相談すると具体的な方法を案内してもらえます。
遠方からでも、誠実に状況を説明することが大切です。
転送できない郵便物とその管理方法
すべての郵便物が転送できるわけではありません。
特に本人確認が必要な郵便物は、転送不可となります。
転送できない主な郵便物
転送不可の郵便物は、配達時に不在であれば「不在票」が投函され、7日以内に受け取りがなければ差出人に返送されます。
このため、定期的に本人の郵便受けを確認し、不在票が入っていないかチェックしておくことが重要です。
また、差出人が明記されている場合は、返送前に連絡を取り「本人が勾留中で受け取れない旨」を伝えておくと、再送や保留の対応をしてくれることもあります。
郵便物が転送されない場合に気づく方法
転送届を出していても、すべての郵便物が正しく転送されるとは限りません。
特に、本人確認が必要な郵便物や、住所の記載に不備がある場合は、郵便局で止まってしまうことがあります。
逮捕・勾留中の本人とは直接連絡が取れないため、家族側で気づく工夫が必要です。
家族が気づける主なサイン
- 郵便受けに「不在連絡票」が入っている
➡ 転送できない郵便物(書留など)が届いていた証拠です。早めに内容を確認し、差出人に連絡を取りましょう。 - 同じ差出人(銀行・役所など)からの通知が以前と比べて届かない
➡これまで毎月届いていた通知が急に途絶えた場合、返送されている可能性があります。 - 家族あてに、差出人から「本人宛郵便が戻ってきた」と連絡が入る
➡まれに、契約書などで緊急連絡先として家族の電話番号が登録されている場合があります。
このようなときは、返送理由を確認し、必要に応じて家族宛て再送や住所変更を依頼します。 - 弁護士を通じて、本人宛の重要書類が届いていないと知らされる場合
➡ 弁護士が行政機関や金融機関とのやり取りを行っているときに、郵便物の返送を把握して知らせてくれることがあります。
家族ができる確認方法
- 転送届を出した郵便局に、定期的に転送状況を確認する
- 書留などの不在票が入っていた場合、差出人に直接問い合わせる
- 重要そうな差出人(市区町村・銀行・年金機構など)に、本人宛郵便が届いていないか確認する
これらを行うことで、転送が滞っていることを早めに把握できます。
本人とは直接連絡が取れない状況だからこそ、家族が「郵便の動き」に目を配ることが大切です。
面会や弁護士を通じて確認しておきたい郵便・手続き関係
逮捕・勾留中の本人とは、電話やメールで直接やり取りができません。
しかし、留置場での面会や手紙のやりとり、弁護士との面談を通して、本人の意向や未処理の手続きを確認することができます。
これは、家族ができる大切なサポートのひとつです。
面会や手紙で確認しておくとよいこと
- 勾留前に届いていた郵便物のうち、重要そうなものがないか
- 本人がやり取りしていた銀行・役所・会社などの通知の有無
- 滞納・支払い・契約更新など、期限が迫っていそうなものがないか
- 家族が転送届を出してもよいかどうか(本人の同意確認)
手紙で確認する場合は、検閲(内容確認)が行われるため、個人情報や事件の詳細には触れず、
「郵便物の管理について確認したい」といった簡潔な内容で伝えるようにします。
弁護士を通じてできること
弁護士は、本人との連絡手段を持っている唯一の存在です。
そのため、郵便物や行政手続きの代理対応が必要な場合は、弁護士を通じて確認・依頼するのが確実です。
- 転送できなかった郵便物があるか確認してもらう
- 行政機関や金融機関との書類のやり取りを代理で進めてもらう
- 本人の意向に沿って、家族が行うべき手続きを整理してもらう
弁護士は守秘義務を負っており、プライバシーにも配慮して対応してくれます。
面会や連絡の際に「郵便物関係で気をつけることはありますか?」と一言尋ねてもらうようにお願いするだけでも、トラブルの防止につながります。
また、面会や手紙のやりとりの中で、本人から「これを差し入れてほしい」と頼まれることもあります。
留置場や拘置所では、持ち込みに制限があるため、許可された品を安全に届けてくれる代行サービスを利用する方法もあります。
「さしいれや」では、全国の留置場・拘置所に対応しており、家族の代わりに必要な物品を届けることができます。


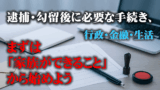

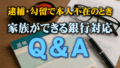
これは「宛所不明」ではなく、「配達先は存在するが受取人不在」という扱いで、
一般的に7日以内に受け取れない場合、郵便局から差出人に返送される仕組みです。