家族や友人が突然逮捕されてしまい、保釈の話が出たときに「保釈保証金が用意できない……」と困る方も少なくありません。本記事では、保釈保証金についての基本的な知識や、用意できない場合の解決策についてわかりやすく解説します。
保釈保証金とは?納めなければどうなるのか
保釈保証金の基本
保釈保証金とは、裁判所が被告人を一時的に釈放する際に支払う金額です。これは被告人が裁判にきちんと出廷することを保証するための制度で、裁判終了後に判決にかかわらず返還されます。ただし、逃亡したり裁判所の決まりを守らなかった場合は没収されることもあります。
保釈保証金を納めなければ?
保釈保証金を納められない場合、基本的には留置場や拘置所に留め置かれたままになります。これにより、被告人は自由を制限され続け、社会生活や仕事に支障が出ることになります。
保釈保証金を準備できない場合の選択肢
家族や友人に相談する
まず最もシンプルな方法は、家族や友人に協力を依頼することです。保釈保証金は、被告人本人ではなく家族や知人が支払うことも可能です。支援してくれる人がいるかどうか、相談してみましょう。
「日本保釈支援協会」を利用する
「日本保釈支援協会」は、保釈保証金の立替支援を行う一般社団法人です。保釈保証金の準備が難しい方々に対し、迅速かつ適切な支援を提供しています。
サービス内容
同協会は、被告人やその家族が保釈保証金を用意できない場合に、保釈保証金の立替を行います。これにより、被告人は拘束状態から解放され、社会生活を継続しながら裁判に臨むことが可能となります。
利用の流れ
- 申し込み:協会のウェブサイトや電話を通じて申し込みを行います。
- 審査:申込内容に基づき、協会が審査を実施します。
- 契約:審査通過後、協会と契約を締結します。
- 保釈保証金の立替:協会が裁判所に保釈保証金を納付し、被告人の保釈が実現します。
手数料
サービス利用には、立替金額に応じた手数料が必要です。詳細な料金体系や支払い方法については、協会の公式ウェブサイトをご確認ください。
「全国弁護士協同組合連合会の保釈保証書発行事業」を利用する
「全国弁護士協同組合連合会(全弁協)の保釈保証書発行事業」は、経済的理由で保釈保証金を用意できない被告人のために、全弁協が保証書を発行し、保釈を支援する制度です。この制度により、被告人は実際の保証金を用意することなく保釈が可能となり、資金的に厳しい方にとって非常に有益な手段となっています。
制度の目的
この事業は、経済状況による不平等を解消し、被告人の人権を守ることを目的としています。逃亡や証拠隠滅の可能性が低く、保釈が適当と判断される被告人であっても、保証金を用意できない場合、拘束が続いてしまいます。全弁協は、弁護人の申請に基づき保証書を発行し、万一の場合の保証金支払いも全弁協が行います。これにより、弁護人個人のリスクを軽減し、資金が乏しい被告人にも平等に保釈の機会を提供することを目指しています。
利用手続き
利用するには、まず担当弁護人が所属する弁護士協同組合を通じて全弁協に事前申込みを行います。申込みには、保証委託者(通常は被告人の身元引受人)の住民票や収入・資産を証明する資料が必要です。審査を通過すると、全弁協と保証委託者との間で「保釈保証委託契約」を締結し、保証料や自己負担金を支払います。その後、全弁協が保釈保証書を発行し、弁護人を通じて裁判所に提出することで、被告人の保釈が実現します。
審査基準
審査では、保証委託者の収入や資産状況が評価されます。具体的には、収入額、勤続年数、債務の有無、住居費などが考慮され、保釈保証金が没収された場合に支払い能力があるかが判断基準となります。収入が少ない場合でも、資産を所有していれば審査が通る可能性があります。また、保証委託者が複数いる場合、その収入を合算して審査することも可能です。
保証料と自己負担金
保証料は、保証する金額の一般事案で2%、薬物事案では3%となっています。さらに、薬物事案の場合は、保証金額の20%を自己負担金として預託する必要があります。自己負担金は、保釈期間中に問題がなければ全額返金されますが、保証金が没収された場合には、全弁協が裁判所に納付した金額から自己負担金を差し引いた金額を保証委託者が支払うことになります。
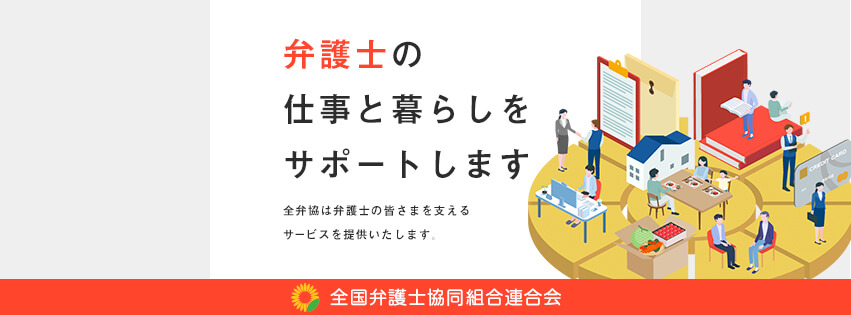
このように、全弁協の保釈保証書発行事業は、経済的に困難な状況にある被告人やその家族にとって、保釈を実現するための重要な支援制度となっています。
弁護士は保釈保証金を建て替えてくれるのか?
弁護士は原則として保釈保証金を建て替えることはありません。ただし、依頼者の状況に応じて、「日本保釈支援協会」や「全国弁護士協同組合連合会」の制度を紹介してくれる場合があります。弁護士と相談しながら、適切な方法を探しましょう。
金融機関から保釈保証金を借りることはできる?
金融機関(銀行や消費者金融)から保釈保証金を借りることも理論上は可能ですが、以下の点に注意が必要です。
- 申し込みから融資実行まで時間がかかる
- 収入や信用情報によっては審査に落ちる可能性がある
- 高額な利息が発生する場合がある
保釈保証金の準備が難しいときの最善策
早めに弁護士に相談する
保釈保証金の準備が難しい場合、まず弁護士に相談することが重要です。弁護士は状況を判断し、「日本保釈支援協会」や「全国弁護士協同組合連合会」など、最適な支援を提案してくれます。
公的支援制度の活用
一部の自治体では、経済的に困難な人向けの支援制度が存在することもあります。自治体の福祉窓口などに相談してみるのも一つの方法です。
複数の手段を組み合わせる
1つの方法だけでなく、家族や友人からの支援、公的制度、弁護士のサポートを組み合わせることで、保釈保証金を確保する道が開けることもあります。
まとめ
保釈保証金を用意できない場合でも、適切な対処法を知っておくことで、保釈の可能性を高めることができます。本記事で紹介した「日本保釈支援協会」や「全国弁護士協同組合連合会(全弁協)」の支援制度を活用すれば、資金が不足していても保釈を実現できる可能性があります。
また、家族や友人からの支援を得ること、公的な支援制度を活用すること、さらには弁護士に相談して最善策を探ることが重要です。金融機関から借りる選択肢もありますが、審査の難しさや高額な利息などリスクも伴うため、慎重に検討する必要があります。
保釈は、被告人が裁判に臨みながら社会生活を継続するための重要な手段です。しかし、保証金を用意できないことで長期間の拘束を余儀なくされるケースもあります。そのため、早めに弁護士と相談し、利用できる支援制度について正しい情報を得ることが大切です。
保釈保証金の準備が難しいときのポイント
- まず弁護士に相談する:状況に応じた適切な支援制度を提案してもらえる。
- 「日本保釈支援協会」の活用:保釈保証金を立て替えてもらうことで、迅速な保釈が可能。
- 「全国弁護士協同組合連合会」の制度を利用:経済的に困難な場合でも、保釈保証書による支援を受けられる。
- 家族や友人の支援を検討:保釈保証金は第三者が支払うことも可能。
- 金融機関の融資を検討(注意点あり):時間がかかる場合や高額な利息が発生するリスクを理解する。
- 自治体の公的支援制度の確認:一部の自治体では、経済的支援が受けられることもある。
保釈保証金が準備できないときは、一人で悩まず、できるだけ早く弁護士に相談し、複数の手段を組み合わせて最適な方法を選ぶことが大切です。





