逮捕や勾留によって本人が自宅に戻れない状況になると、家族は突然「生活費が引き出せない」「公共料金が払えない」といった現実的な問題に直面します。
本記事では、本人が銀行口座を使えなくなった場合に、家族がどこまで対応できるのかをQ&A形式で実例をもとにわかりやすく解説します。
Q. 逮捕されると銀行口座はどうなる?
逮捕や勾留を理由に、銀行口座が自動的に「凍結(利用停止)」されることは 基本的にありません。
つまり、警察や検察が銀行に連絡して口座を止めるということは通常は行われません。
ただし、以下のようなケースでは例外的に凍結されることがあります。
- 本人が振り込め詐欺やマネーロンダリングなどの金融犯罪に関与した疑いがある場合
- 銀行が警察や裁判所からの照会・差押命令を受けた場合
- クレジットカードの延滞やローンの不払いによる信用情報上の制限
このような特別なケースを除けば、逮捕直後に口座そのものが使えなくなることはありません。
ただし、本人が留置場や拘置所にいる間は、当然ながら 本人自身がATMや通帳を使うことはできません。
Q. 家族が本人の預金を引き出すことはできる?
結論から言うと、家族であっても勝手に引き出すことはできません。
銀行口座はあくまで「名義人本人の財産」であり、たとえ配偶者や親子であっても、正規の手続きがない限り、法的には他人の口座です。
❌ カードや通帳を使った入出金・残高照会はすべて禁止
たとえ本人から「使っていい」と頼まれたとしても、また委任状を預かっていたとしても、正規の手続きを経ずにATMなどで入出金や残高照会を行うことは、銀行規約に反し、場合によっては刑法上の犯罪(窃盗罪・電子計算機使用詐欺罪など)に問われる可能性があります。
これは親子・夫婦・兄弟であっても例外ではありません。
銀行のシステム上、残高照会も“取引行為”として記録されるため、本人以外の操作は「不正利用」として認識されます。
防犯カメラや操作履歴によって後に発覚することも珍しくありません。
✅ 正しい対応方法
どうしても家族が入出金や残高照会を行いたい場合は、必ず銀行窓口で正式な代理手続きを行う必要があります。
- 銀行所定の委任状と本人確認書類を提出
- 「代理人カード」制度がある場合はそれを利用
- 委任状は弁護士を通して作成するのが望ましい
本人の自筆のメモ(許可書)を持っていても、ATM操作は銀行上「第三者利用」とみなされるため避けましょう。
⚠️残高照会も同じく「本人以外の利用」は禁止
入出金と同様に、残高照会(残高確認)も本人以外が行ってはいけません。
キャッシュカードや通帳を使い、暗証番号を入力して残高を確認する行為も、銀行では「取引操作の一種」として管理されています。
そのため、本人以外の家族がこれを行うと、銀行のシステム上では「不正アクセス」「第三者による利用」として記録されます。
実際に、残高照会だけでも銀行が「不正利用の疑い」として口座を凍結した例があります。
本人から頼まれても、キャッシュカードや通帳を使ってATMでお金を動かすことはできません。
残高照会を含め、すべて銀行窓口での正規の代理手続きが必要です。
委任状は弁護士を通して作成するのが最も確実です。
Q. 家族が本人の口座に入金することはできる?
こちらは状況が異なります。
本人の通帳やキャッシュカードを使って入金することは避けるべきですが、家族自身の口座から本人の口座に振り込む行為は問題ありません。
振込はあくまで「自分の資金を自分の意思で他人に送る行為」なので、法的にも銀行規約上も正当な取引として扱われます。
ただし注意が必要なポイント
- 本人の口座が凍結・差押え中の場合、振込が反映されず返金されることがあります。
- 振込額が極端に多い場合や短期間に繰り返す場合、銀行から不審取引として照会を受けることがあります。
- 税務上も、高額送金は「贈与」とみなされる可能性があるため注意しましょう。
安全な振込の目安
- 振込目的が「光熱費」「家賃」「通信費」など生活費である場合
- 金額は必要最低限の範囲にとどめる(例:月数万円程度)
- 振込明細を残しておく(後で説明が必要になったときに役立つ)
💡 振込目的を「光熱費」「生活費補助」など明確にしておくと、後から説明しやすく安心です。
避けるべき行為
- 本人のキャッシュカードや通帳を使ってATMで入金すること
→ 本人以外の操作となり、銀行規約違反です。 - 他人名義の口座や第三者経由での複雑な送金
→ マネーロンダリング(資金洗浄)対策に抵触する可能性があります。
家族が自分の口座から本人の口座へ振り込むことは問題ありません。
ただし、凍結や差押えの有無を確認し、金額は必要最小限に。
光熱費や家賃などの支払いに備える範囲で行いましょう。
本人のカードや通帳を使って入金する行為はNGです。
Q. 給与の振込や自動引き落としはどうなる?
逮捕や勾留によって本人が銀行を利用できなくなっても、銀行口座そのものが自動的に止まるわけではありません。
したがって、給与の振込や公共料金などの自動引き落としは、基本的にこれまでどおり処理されます。
しかし、残高不足や勤務先との契約停止などにより、引き落としや振込が滞るおそれがあります。
その結果、延滞・滞納が発生し、信用情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるリスクもあります。
家族ができる対応策
- 光熱費や家賃など、引き落とし口座を家族名義に変更しておく
- 勤務先に事情を説明し、給与の振込先を見直す(一部を家族口座に分けてもらうなど)
- 弁護士を通じて、本人の意思確認や必要な書面(委任状等)を整える
💡あらかじめ、生活費や支払い口座を整理しておくと、逮捕・勾留時の混乱を防げます。
このように、口座が使えなくなる前に
「支払い」「振込」「引き落とし」を誰がどの口座で行うかを明確にしておくことが大切です。
銀行アプリの共有は避けましょう
銀行アプリやインターネットバンキングのIDやパスワードを家族で共有することは避けてください。
ほとんどの銀行の規約で、ログイン情報の共有や代理操作は禁止されています。
「ファミリー口座照会サービス」を利用している場合は、登録されている家族は、利用履歴や残高を参照することができますが、「ファミリー口座照会サービス」を利用するには、逮捕前に本人による登録操作が必要となります。
本人以外がアプリにアクセスすると、銀行側で不正利用とみなされ、口座の凍結や取引停止につながるおそれがあります。
また、不正送金などが発生した場合、補償の対象外になることもあります。
もし残高や引き落とし状況を確認したい場合は、必ず銀行窓口で正式な代理人手続きを行いましょう。
銀行によっては「代理人カード」や「委任による照会制度」が用意されています。
不安な場合は、弁護士を通じて口座状況を確認してもらうのが最も安全です。
Q. クレジットカードやローンの支払いは?
クレジットカードやローンは、口座の自動引き落としが継続される限り、支払いも続行されます。
ただし、逮捕・勾留により給与が止まる、残高が不足するなどの理由で、延滞や滞納が発生するおそれがあります。
延滞が続くと信用情報に記録され、今後の契約やローン審査に影響するため、できる限り早めに対応することが大切です。
家族が代わりに払える?
家族ができる最も安全な方法は、本人の口座に必要な金額を振り込んでおくことです。
こうすることで、引き落とし日までに残高が確保され、カード会社や銀行に余計な確認を取る必要もありません。
この方法であれば、法的にも銀行規約上も問題ありません。
ただし、口座が凍結されている場合は振り込みが反映されないため、事前に銀行や弁護士を通じて確認しておきましょう。
代理返済について
カード会社や銀行によっては、事情を説明すれば家族による代理返済を認めるケースもあります。
ただし、すべての金融機関で可能ではなく、手続きも煩雑です。
この場合は、
- 事情を正直に説明する
- 家族関係を証明する書類(戸籍謄本など)を提出する
- 必要に応じて弁護士を通す
といった手続きが求められます。
ただし、金融機関ごとに対応方針が異なるため、原則は本人の口座に振り込む形で支払いを維持する方が確実です。
延滞を防ぐためには、まず本人の口座に振り込んで残高を確保しましょう。
代理返済は特例的な措置として考え、銀行やカード会社に確認のうえで行うのが安全です。
逮捕された本人の口座を操作するための銀行窓口で正規の代理手続き
家族が本人の代わりに銀行口座を扱いたい場合は、銀行窓口で「正規の代理手続き」を行う必要があります。
事情を説明するだけでは、銀行は残高照会や出金を認めません。
代理手続きでできること・できないこと
必要書類
- 本人の署名入り委任状(銀行所定用紙が望ましい)
- 本人の身分証コピー(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 代理人(家族)の身分証
- 家族関係を証明する書類(戸籍謄本・住民票など)
💡委任状は弁護士を通して作成するのが最も確実です。
💡弁護士作成の書面は銀行でも信頼度が高く、スムーズに受理されます。
手続きの流れ
- 弁護士が本人の意思を確認し、委任状を作成
- 家族が書類を持って銀行窓口へ提出
- 銀行が本人・代理人の身元確認を実施
- 内容確認後、手続き可否を判断
支店によっては即日対応できない場合もあります。
事前に電話で確認するとスムーズです。
注意点
- 委任状があっても、高額取引や解約は弁護士同行が必要な場合があります。
- 本人が勾留中で来店できない場合は、弁護士による意思確認書付きの委任状が求められることがあります。
- 手続きは銀行ごとに異なるため、正直に「本人が勾留中」である旨を伝えて相談しましょう。
<参考>主要銀行の代理手続きページ
各銀行では、本人が来店できない場合の「代理手続き」に関する案内ページが公開されています。
具体的な書類や必要な手順は以下をご確認ください。
【三井住友銀行】代理人指名手続
【みずほ銀行】代理人カードを作成したい
【三菱UFJ信託銀行】家族等の名義の預金について手続きをする
Q. 本人の口座が凍結されている場合
逮捕・勾留をきっかけに、本人の口座が「凍結」されることがあります。
この場合、家族がATMや窓口で操作したり、解除を求めたりすることはできません。
凍結の主な理由
- 捜査機関(警察・検察)が、犯罪の証拠や資金の流れを調べるために差押えを行った場合
- 銀行が、不正利用の疑い(マネーロンダリング・振込詐欺など)で口座を一時停止した場合
- 裁判所の命令による差押えや強制執行が行われた場合
これらはいずれも、銀行の判断や公的機関の命令によって止められている状態です。
家族ができること・できないこと
凍結解除を依頼する
❌(銀行は本人または弁護士からの依頼しか受け付けない)
凍結理由を確認する
⚠️(弁護士を通じてなら可能。家族単独では不可)
入金する
❌(凍結中は入金も反映されない場合が多い)
弁護士に委任して調査依頼
✅(唯一可能な安全な手段)
正しい対応方法
凍結解除や理由確認は、弁護士を通して行うしかありません。
弁護士であれば、
- 捜査機関への照会
- 銀行への問い合わせ
- 差押命令の有無の確認
を正式に行うことができます。
家族が独自に銀行に問い合わせても、「個人情報のためお答えできません」と言われるのが通常です。
本人の口座が凍結されている場合、家族は直接何もできません。
解除や状況確認は弁護士に一任するのが唯一の正しい方法です。
無理に動こうとすると、かえって不正アクセスや情報漏えいと誤解されるおそれがあります。
家族ができる対応と注意点
逮捕や勾留は、本人だけでなく家族の生活にも大きな影響を与えます。
銀行対応では、「何ができて、何ができないか」を冷静に整理することが大切です。
家族ができる主な対応
- 銀行窓口で正式な代理手続きを行う
- 弁護士を通じて本人の意思を確認する
- 本人の口座に生活費を振り込む
- 支払口座を家族名義に変更しておく
焦らず、正しい手続きで進めることで、トラブルを防ぎながら生活を守ることができます。

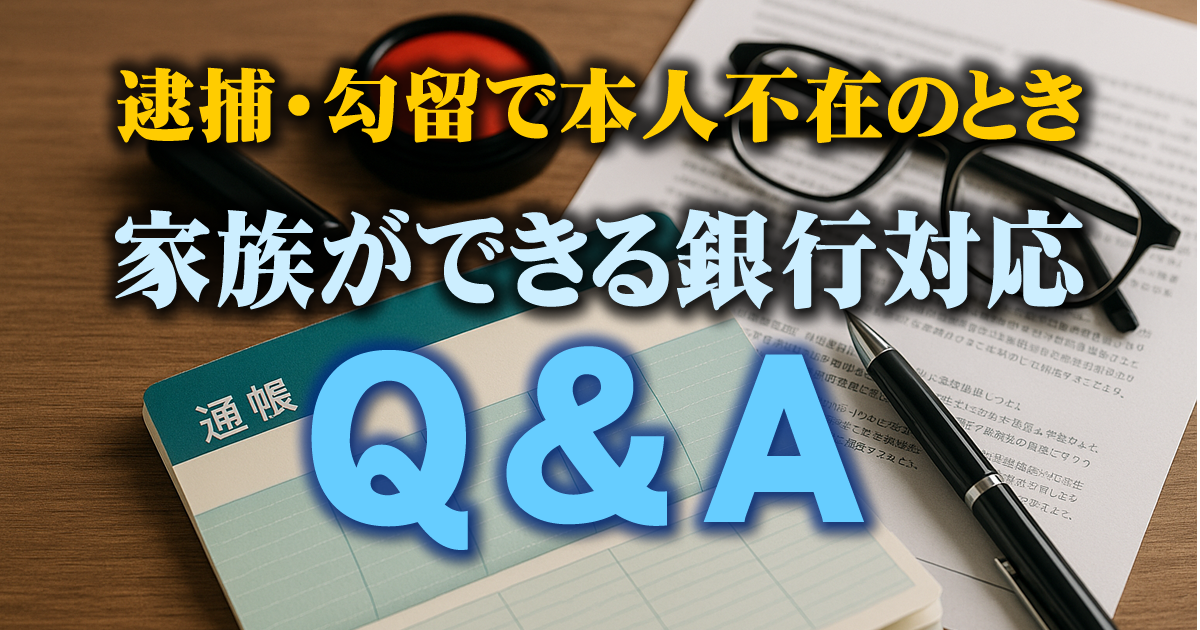

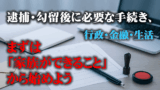

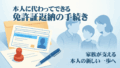
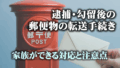
自動引き落としは基本的に継続されますが、残高不足には注意が必要です。
銀行アプリの共有は避け、代理手続きや弁護士経由で安全に対応しましょう。